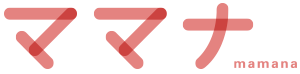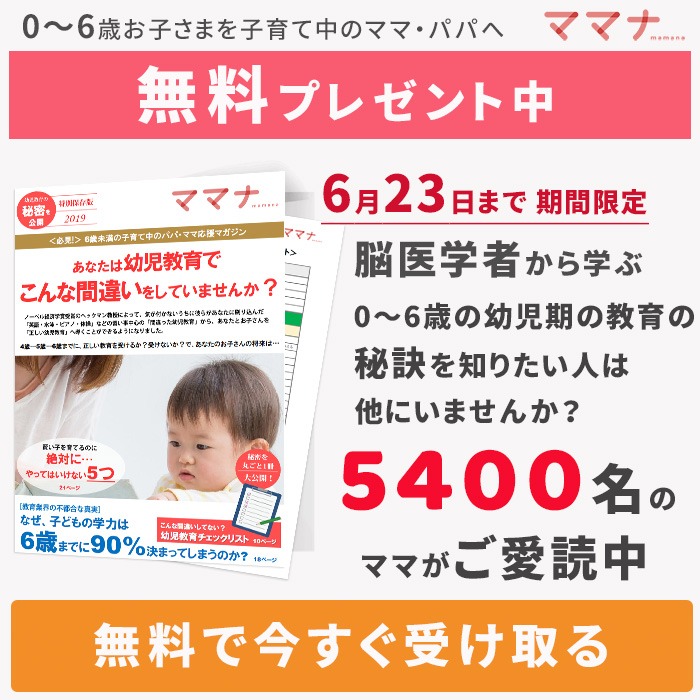少子化や親の高学歴化を背景に、自身の子に小学校受験をさせたいと考える人は年々増加しています。
そんな小学校受験に欠かせないのが、“お教室”と呼ばれる小学校受験のための幼児教育に特化した幼児教室です。
今回は、そんな幼児教室を含めた小学校受験のための幼児教育と、受験に合格しその後のキャリアを積んでいる先輩たちのキャリアについて、体験談をもとにご紹介したいと思います。
小学校受験のための幼児教育とは?

専門家の中には、小学校受験をするなら幼児教育が不可欠と考える人が大勢います。
その理由は、多くの小学校受験で採用されている「ペーパーテスト」「絵画工作」「行動観察」「運動」のテストが独特であるためです。
これらのテストに合格する力というのは、生活や遊びを通して身に付けられるものと言えますが、問題形式が独特なため保護者による教育だけでは合格することは不可能と言えるのです。
そのため、小学校受験を目指す多くの家庭では、効率的に受験対策をおこなうために、幼児教室に通うことになります。
もちろん、受験対策として特殊な教育を受けさせる以外にも重要な教育があります。
それが家庭での教育です。
躾や基本的な生活習慣を身につけさせることが中心となりますが、合格者の中には様々な教育法を取り入れている家庭が見受けられます。
「絵画」を自宅で指導したケース
「絵が得意じゃないと、自由に描くのは難しい。
絵が好きでも、毎回違うテーマだと、迷ってしまうこともあります。
なので、ある程度パターン化してあげると、描くのが楽になり、子供はどんどん描くようになります。
例えば、
「幼稚園で遊んでる」→自分を描いて、お友達を描いて、遊具を背景に描く
「動物園に行く」→自分を描いて、家族を描いて、背景に動物を描く
といった感じ。
うまく描けた絵があれば、壁に貼ってあげるといいですよ。
喜びますし、似たようなテーマが出た時に、それを思い出して描くのにも役立ちます。」
上履きにも受験対策したケース
「まさかとは思いますが幼稚園で使ってる上履きを試験の当日使えばいいやなんて思ってはいませんよね?
学校によって名前を書いてください、もしくは名前は書かないでくださいなど指示があります。
受験用にきちっと用意しておかないと大変なことになりますよ。
だからといって大事にしすぎて当日初めて履いた、前日履いたでは困ります。
靴は履き心地がありますメーカーによって微妙にサイズも違います。
ちゃんと足に合っているのか?
走った時に脱げないか?
子供が一人で脱ぎ着できるか?
それから初めて剥いてしまうと脱いだ時にどれが自分の靴かわからなくなってしまうことがあります。
トイレに行って脱がなくてはいけない学校、マットの上がり。
脱いだはいいがあまり見たことない上履きだったから、自分のかわからずにノロノロダラダラキョロキョロこれでは印象も台無しです。
お教室で何度か運動の時に履いてみたい自分の足に馴染むようにきちんと準備しておくのが親としての役目です履きやすい脱げにくいというのでこの教育シューズとってもいいですね。
履いてる人もたくさんいますからどれが自分のかわからなくならないように注意!」
小学校受験の準備はいつからはじめるべき?

小学校受験専門の幼児教育運営者であるアンテナプレスクール校長の石井至氏によると、幼児教室に通わせるのに適している子どもの年齢は、幼稚園や保育園の年少クラス(3歳クラス)。
教室の中には0歳から通えるクラスもありますが、年少からのスタートでも十分に効果が得られるとのことです。
特に受験項目として出題されることの多い「絵画」や「行動観察」は、家庭での教育が難しく、教室での特別な指導が必須です。
以下では、それぞれの項目についてスタートすべき年齢や方法をご紹介します。
「絵画」
年少からじっくりと取り組ませるのが効果的。最初は子どもの自由な発想に任せて好きな絵を描かせましょう。
受験においては出題された内容を指示通りに描く必要があるので、そうした訓練も必要になりますが、幼児教室に通えばすぐに描けるようになる子が多いです。
「行動観察」
年中から取り組むのが一般的。数人の子どもと一緒にゲームやグループでの遊びをします。
協調生やリーダーシップの才能などを見られますが、子どもごとの特性を見る試験であるため、対策については各教室のノウハウに頼るしかないのが実際のところです。
「ペーパーテスト」
年中あたりから取り組むのがおすすめ。あまり早い時期にスタートすると、言葉の意味が理解できないため、効率的ではありません。
おおよその言葉が理解できる年長の1年でしっかりと対策するのが効果的と言えるでしょう。
〜体験談〜小学校受験を経験した子どものその後の人生

ここでは、体験談をもとに小学校受験を経験した子どもたちのその後のキャリアについてご紹介します。
国立小学校受験経験者のケース
「私は小、中と国立で高校から私立に行き、今は研究職に就いています。
国立は教育設備がある割に適度に競争力も求められ、でも学費安くておすすめです。
(質問者が)私学しか知らないから仕方がないかもしれませんが、教育スタイルも無限にバリエーションがあって実は面白いですよ。」
こちらの体験談は、国立の小学校を経験し、現在は社会人として研究職に就き活躍されている方が書かれたものです。
小学校受験と聞くと私学を思い浮かべがちですが、国立の小学校であれば教育設備が充実していることや学費が安く済むというメリットがあるようですね。
また、こちらの方はそんな施設での教育成果を現職に着く大きなきっかけとされているようです。
私立女子小学校の1年生のケース
「1年生もまもなく終わる今、振り返ってみて。
あの自由気ままな5ヶ月(入学まで)の間に、あれ準備しておけばよかった~これしておけばよかった~と、思うことが多々あります久しぶりのブログは、それを紹介したいとおもいます。
ひとつ目がコチラ。
読書力をUpさせておくこと!私立小、一年生女子の読書力、想像以上にレベル高しです入学前には、美しい文字を~なんて思っていましたが、注力ポイントはここじゃなかった・・・。
書く力は、付け焼刃の母が教えるより、学校に入ってから丁寧に教えてもらったほうがよいというのが私の感想。
たしかに、幼児教室の先生も、文字は学校によって教え方がいろいろあるので、やる必要なしと。(といっても、一応一通り皆さん書けますが)
実際、娘の学校もそうですが、女子校の多くが美しい文字を書くことにはかなり力をいれています。」
こちらは、私学の女子小学校に入学したお子さんの1年間を経た体験談です。
体験談によると私立の女子小学校の児童は読書力が高いらしく、合格から入学までの準備期間で読書力を高められなかったことを反省されている様子が伝わってきます。
中学受験を経て医学部に入ったケース
「最近、お子さんを医学部にいれたお母様と知り合い、たくさんの体験、勉強の話しを聞かせていただき、中学受験の大切さやお金の大変さ(笑)を学びました。
小学校受験は、心の教育や教育方針のあった環境での子育て、そういったことを大切に考えることが大切ですよね。
我が家も、どうするかはまだわかりませんが、どう転んでもよいように、小学校受験の頃と同様の朝夜の勉強は、今も続けています」
こちらは、ママ友から中学受験を経て医学部入学したお子さんについて、聞いた体験談。
ご自身は上の子(女児)を小学校受験で私学に通わせていて、下の子(男児)のキャリア形成について相談された模様。
小学校受験をする際に必要なことが、「心の教育」や「教育方針」ということに気づかれた貴重な体験談になっています。
小学校受験をするなら、まずは家庭の考えに合う幼児教室を探すべし

小学校受験の特性上、家庭での教育だけでは受験合格は不可能と言えます。
そのため、小学校受験を目指すのであれば、まずは家庭や子どもに合った幼児教室を探すことが先決と言えますね。
また、小学校受験についての議論には様々なものがありますが、受験先の小学校やその後に続く中高一貫教育を経て活躍している人が大勢いるのも事実。
受験をゴールにすることなく、進学先の環境をうまくその後のわが子のキャリア形成に利用したいものですね。