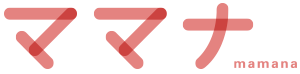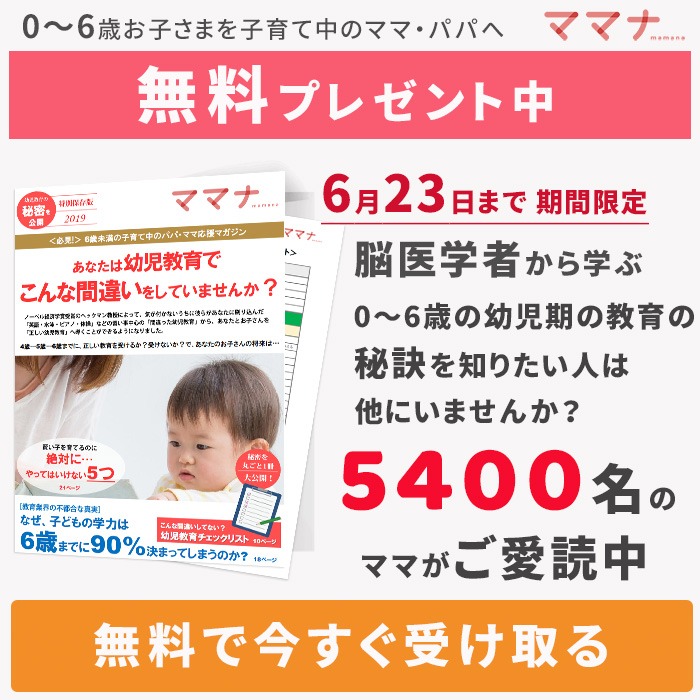子供を持つことは、多くの女性にとっての夢とも言える幸せなことですが、いざ実際に子供が生まれて育児の日々が始まると、その多忙さや悩みの多さにほとんどのママが驚いてしまうもの。
孤立しがちな育児では「こんな風に悩んでいるのは自分だけ?」と感じがちですが、他のママも同じことで悩んだり解決したりを繰り返しています。
今回はそんな子育ての悩みと解決法についてご紹介します。
その1:将来の子供にかかるお金についての悩み

「お金の悩みがなければ子育ての悩みはほとんどなくなる!」と感じているママは多いでしょう。
実際、お金がいくらでもあるなら毎日シッターさんにきてもらうこともできるし、ワーママとして多忙を極めることも無くなるかもしれません。
特に多いのが、子供の将来にかかるお金の悩み。どれだけかかるか正確にわかりづらいのが悩みのもとになっているようです。
解決ポイント
夫婦で子供の教育方針について話し合ってみましょう。
一言に教育費といえども、お医者さんにするための教育費と大学からは奨学金を使って進学する教育費とでは、必要となるお金の額が全く異なります。
一度旦那さんと自分たちの子供をどんな風に育てたいのかを話し合い、必要となるお金を算出しましょう。
不要なストレスを減らせるかもしれません。
その2:産休・育休中にお給料が減る悩み

子供の教育費に次ぐお金の悩みとして多いのが産休・育休を使うことによる手取り額の減少です。
夫婦ともに取得を予定している人ならなおさらでしょう。
解決ポイント
産休中は働いている時よりも手取り額が増えることがあります。
また、育休中も半年間は手取りではなく額面の66.6%がもらえるので、想像しているよりもお給料が減らなかったと感じるママは多いです。
税金などの優遇制度も充実しているので、一度会社にどれくらい手取り額が減るのか?どんな優遇制度があるのか?を確認してみましょう。
その3:配偶者との家事・育児の分担についての悩み

“ワンオペ育児”という言葉が定着した日本ですが、旦那さんの仕事が多忙で家事や育児を手伝ってもらえないというママは多いです。
核家族であることが普通になった日本では、祖父母やおじおばのサポートがないことも珍しくなく、子育てママを孤立化させる原因となっています。
解決ポイント
パパの育休取得が急激に拡大しています。
一昔前は「男が育休を取るなんてありえない!」と言われた日本ですが、今は育休を進んで取る姿は会社や同僚に“革新的な存在”として受け入れられる可能性も。
育休取得とまではいかないまでも、働き方改革の影響で、残業の軽減や有給取得を推進している会社も多いので、パパが家にいる時間をうまく利用し、ママが一人になる時間を作るようにしましょう。
その4:祖父母世代との子育て感の違いによる悩み

核家族化が進んだ日本とはいえ、最も信頼できる先輩ママ・パパである祖父母の意見には耳を傾けたいもの。
しかしながら、昔の子育てと今のそれとでは様々なことが変化しています。
「保育園なんてダメ!」「冬に靴下を履かせないのはかわいそう」と生活の根幹を揺るがす大きなことから些細なことまで、意見が食い違うことは珍しくありません。
解決ポイント
インターネットや専門家の意見を参考に、子育てのトレンドを伝えるようにしましょう。
あくまでも子育ての主役は赤ちゃんとママ・パパです。大きく意見が異なった時は「今の育児はこんな感じだよ」と、ネットや専門家の意見も交えて伝えてみましょう。その5:子育て中にイライラすることへの悩み

子育て中の最も大きな悩みとも言えるのが、子育てにイライラしてしまう感情との向き合い方。
「子供が夜中寝てくれない」「離乳食がうまく進まない」など、すべてのママが子育て中のイライラに悩んでいます。
解決ポイント
「子供は○○するもの」「ママは○○するもの」という固定概念を一度手放してみましょう。
健康な子供に育てるために必要なことを、ママは知らないうちに決めつけています。
子供がよく寝てよく食べることに越したことはありませんが、教科書通りに成長する子供は一人もいません。
意図的に固定概念を手放すクセをつけ、子供の個性に大きな心で向き合ってみましょう。
その6:兄弟姉妹で「かわいい」と思う気持ちに差がある悩み

兄弟姉妹のいるママに多いのが「兄弟姉妹によってかわいさが違う」という罪悪感への悩み。
特に、下の子が生まれたばかりの時に「上の子が憎い」と感じるママが多いようです。
解決ポイント
生まれて間も無くの下の子がかわいく上の子が憎いケースのママの場合、何年経っても同じ感情のままという人は非常に少ないです。
数ヶ月もすると上の子に“お利口さん”な時期が訪れ、下の子に手がかかる時期がやってきます。
数年してもかわいさに差があるという場合は、「親子だって人間だから性格の相性はあるわ」と割り切る気持ちも必要です。
ママと家族との関係でも、全員が同じように仲が良いということはないはずです。
その7:ママ友との人間関係の悩み

赤ちゃんが成長するにつれママ友との関係がスタートします。
「なかなかママ友ができない」と悩むママもいますが、出来たらできたで人間関係に悩んでしまう人が多いです。
「行くたくもないイベントに参加した」「価値観が合わず会うのが億劫」など、悩みはつきません。
解決ポイント
「ママ友は、本当に仲の良い人が1人いればいい」と割り切ってみましょう。今はそんな風に思える人がいなくても、子供が成長するにつれママ友も変化します。そんな歩みの中で気がぴったり合う友達ができるもの。
今はママではない学生時代の友達がママになり、新たな関係を構築できることもあるので、気長に待ってみるのもおすすめです。
その8:子供の癇癪やグズリの悩み

子供の性格は様々ですが、手のかかる子とそうでない子がいるのは事実。
特に、癇癪を持っている子やグズリの激しい子は育児中のママを悩ませます。
ちょっとした外出もままならず、周囲の大人の目が気になって家の中に引きこもりがちになるママもいるでしょう。
解決ポイント
渦中にいるママは、子供に手のかかる時期が永遠に続くように感じてしまいますが、必ず手がかからなくなる時期がやってきます。
また、癇癪やグズリなど、自己主張の激しい子は秘めた才能を持っていることが多いという専門家もいます。
多忙を極める育児中は心に余裕を持つことが難しいですが、子供の個性や成長を楽しみに、数年で終わってしまう貴重な幼少期を大切にしたいものです。
その9:兄弟姉妹げんかへの悩み

一人っ子のママにはピンときませんが、幼児期の子供の兄弟げんかは過酷を極めます。
善悪の判断がつかない上の子が、ママが目を離した隙に下の子を激しく攻撃してしまい、大怪我をおったという事例も散見されます。
ママは片時も目を話すことができず、大きなストレスを感じるものです。
解決ポイント
パパや両実家、一時保育などのサポートを積極的に利用してみましょう。
大けがにつながる可能性がある以上、ママが一人で育児している時には子供たちから目を離すことはできません。
24時間、子供に気を取られている生活が続くと、ママの心身にも悪影響を及ぼします。
周囲のサポートをうまく利用して、ママがリラックスできる時間を作るようにしましょう。
その10:教育方針への悩み

習い事は何をどのくらいさせるのか?どのタイミングで受験させるのか?など、子供の教育方針についての悩みはつきません。
お金や時間の問題とも絡んでいるので、ママ一人では抱えきれない悩みと言えるでしょう。
解決ポイント
夫婦でしっかり話し合う必要があります。子供の教育を考えるのは、ママだけの役目ではありません。
パパや必要であれば祖父母も交えて、家庭それぞれの考える理想的な教育方針を見つけ出しましょう。
子育てに悩みはつきもの、一人で悩まず時にはプロの力も借りてみる

子育てに悩みのない人はいません。
地域のアドバイザーや教室の先生など、初めは相談することにハードルを感じますが、プロの意見に耳を傾けてみると、目からウロコの発見が得られることもあります。